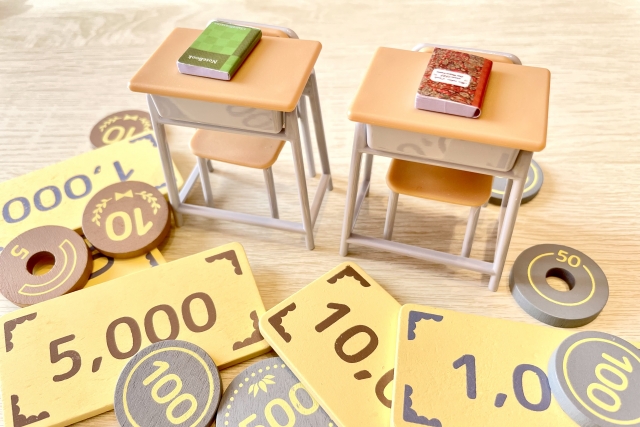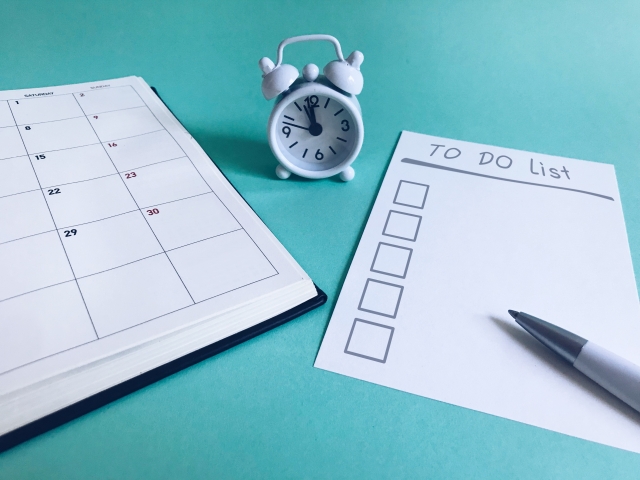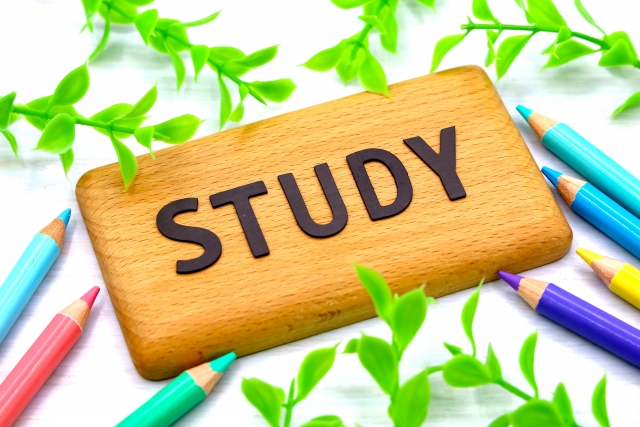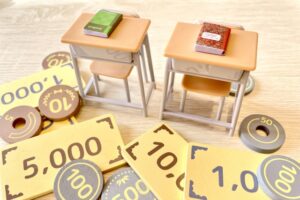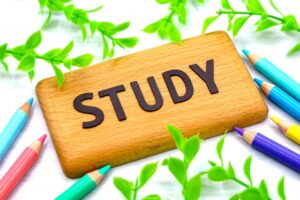「ZEN大学って実際どうなの? 社会人が年間38万円も払って学び直す価値はある?」
そんな疑問をお持ちではないでしょうか。
2025年に開校したばかりのZEN大学。私自身、社会人として働きながら学んでいますが、早くも半年が経過しました。
今回は、現役学生である私が感じたリアルな感想と、どんな人なら「お金を払ってでも学ぶ価値があるか」を本音でレビューします。
まずは学費の話。月々3万円の自己投資
ZEN大学の学費は、年間38万円。月々に換算すると約3万2千円です。 初年度はこれに加えて、入学検定料(3万円)と入学金(3万6千円)が必要になります。
決して安い金額ではありません。働きながらこの学費を払い、さらに貴重な時間を投資する価値は本当にあるのでしょうか。
ZEN大学の学び方:「広く浅く」が基本スタイル
ZEN大学は「知能情報社会学部」の1学部のみ。その中に6つの専門分野が用意されています。
- 数理
- 情報
- 文化・思想
- 社会・ネットワーク
- 経済・マーケット
- デジタル産業
大きな特徴は、これら6分野すべてに必修科目が設定されていること。「経済だけを専門的に学びたい」といった、特定の分野に特化した学習はできません。
もちろん、必修科目以外は自分の興味がある分野の授業を集中して履修することは可能です。しかし、基本的には幅広い分野の基礎を体系的に学ぶスタイルだと感じました。
授業の難易度は? SEの私が感じたこと
「授業は難しい? それとも簡単?」
これは気になるポイントですよね。結論から言うと、個人の知識レベルや経験によって体感が全く異なります。
私の場合、現役のSE(システムエンジニア)なので、「情報」分野の授業はこれまでの知識を再確認するような内容が多く、復習として非常に役立ちました。
単なる基礎知識の羅列ではなく、重要なポイントが凝縮されているため、「本で1から学ぶより効率的に要点だけを学び直せる」というメリットを強く感じました。知っているつもりの内容でも、新たな発見があるのは嬉しい驚きです。
一方で、全く馴染みのない分野の授業は、正直に言って「難しい」と感じることも多々ありました。「へぇ、そうなんだ」とその場では理解できても、記憶に定着させるには相応の努力が必要です。
それでも、これまで触れることのなかった知識を得られたことは、間違いなくプラスになったと感じています。
【最重要】時間の壁。1日2時間の確保が最低ラインか
社会人学生にとって、最も大きな課題は「時間の確保」です。
ZEN大学の授業は、基本的に以下のセットで構成されています。
- 1回約10分の講義動画 × 6回
- 各動画後の確認テスト
- 単元ごとのレポート
これを15回繰り返して1つの履修が終わります(中には別で単位認定試験がある科目もあります)。
1本の動画が10分程度と細かく区切られているため、通勤中の電車内や昼休みといったスキマ時間を活用して学習を進められるのは、社会人にとって大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、単純計算でも1科目(2単位)を修了するのに約20時間は必要です。卒業には124単位が必要なので、4年間で計画的に単位を積み重ねなければなりません。
例えば、片道1時間の通勤で、残業なしで働いたとしましょう。
24時間 – 労働8時間 – 通勤2時間 = 14時間
通勤時間1時間をそのまま学習できるわけでもなく、乗り換えや歩いている時間などは学習することができません。
この14時間から睡眠や食事、家事などの時間を差し引くと、平日に勉強できる時間は限られます。通勤時間含めて1日1〜2時間の学習時間を安定して確保できるかが、学びを継続できるかの大きな分かれ道になるでしょう。
残業が多い方や、ご家庭の事情でまとまった時間が取れない方は、「気づいたら授業を全く受けずに学費だけを払っていた…」という事態になりかねません。
まとめ:ZEN大学に価値を見出せる人、そうでない人
開校から半年。私が感じた「ZEN大学で学ぶ価値がある人」は、以下の条件に当てはまる方です。
- 社会人になって10年以上経過し、様々な分野の基礎知識を効率的に学び直したい人
- 平日1〜2時間、さらに休日も学習時間を確保できる人
逆に、最近大学を卒業したばかりの方や、特定の専門分野だけを深く追求したい方には、あまりメリットがないかもしれません。
また、日々の学習時間を安定して確保できない場合は、残念ながら投資した学費が無駄になってしまう可能性が高いと言えます。
まだ半年時点での感想ですが、個人的には「学び直してよかった」と思っています。今後、さらに専門的な授業が増えてくる中で、また新たな発見があるかもしれません。
引き続き、学びの様子はブログで発信していきますので、ぜひ参考にしてください。